当日は99名の皆様にご参加いただきました。
多くの方にご来場いただき、ありがとうございました。
半月の夜、月といっしょに星空を見上げてみませんか。
4月28日 18:00 はまだ日が出ており、空は明るいままです。しかしよく見ると、南の空高くにうっすらと白い半月を見ることができます。昼間の月を望遠鏡で観察してみましょう。
やがて日が落ちると、西の空に明るく輝く星があります。金星です。そして金星と月の真ん中には、火星が赤く光っています。火星の下の方にはオリオン座のベテルギウス、こいぬ座のプロキオン、おおいぬ座のシリウスが形作る冬の大三角形が沈みかけています。
お月見というと満月が定番ですが、半月はクレーターを観察しやすく、満月とはまた違った表情を見せてくれます。望遠鏡を使った月の拡大映像もお楽しみください。

実施要綱
- 日時: 2023年4月28日(金) 18:00~20:00 (雨天中止)
- 場所: 福生市立福生第二小学校 校庭
- 参加費: 無料
- 参加申込: 不要
下記よりメールアドレス登録してくださった方には、当日15:00に実施可否のメールをお送りします。
2023年4月半月講 メールアドレス登録 - お問い合せ先: まると(TEL: 042-848-2245)
- その他
- 小学生以下は大人の保護者の同伴が必要です。
- 感染症の拡大防止とイベント保険のため、受付にてお名前とご連絡先をいただきます。
- 自家用車での来場はご遠慮ください。
いただいた個人情報について
いただいた個人情報は下記の目的にのみ使用します。
- 感染症拡大防止のため、自治体及び関係機関との連携
- イベント保険
ただし、ご登録いただいたメールアドレスは下記の目的にも使用します。
- 当日15:00に行う実施可否の送付
- 今後のイベント案内
- イベント案内が不要の場合は、登録ページのチェックボックスにてご指示ください。
データシート
地点情報
| 地点名 | 福生第二小学校 |
| 緯度 | 35.7247° |
| 経度 | 139.3362° |
| 高度 | 116m |
こよみ
福生第二小学校
日付: 2023年4月28日
出典: 国立天文台暦計算室 こよみの計算
| 事象 | 時刻 |
| 日の出 | 4:53 |
| 月の出 | 11:03 |
| 月の南中 | 18:28 |
| 日の入り | 18:28 |
| 常用薄明の終わり | 18:53 |
| 航海薄明の終わり | 19:26 |
| 天文薄明の終わり | 20:00 |
| 月の入り | 25:11 |
※ 常用薄明: 太陽高度が -6° の時刻。屋外での作業に支障がない程度の明るさ。
※ 航海薄明: 太陽高度が -12°の時刻。水平線が見える程度の明るさ。
※ 天文薄明: 太陽高度が -18°の時刻。天体観測に支障がない程度の明るさ。
月・惑星の高度と方位
福生第二小学校
日付: 2023年4月28日 時刻: 19:00
出典: 国立天文台暦計算室 こよみの計算
| 天体 | 高度[°] | 方位[°] | 視半径[″] | 月齢 | 等級 |
| 月 | 74.2 | 207.9 | 900.1 | 8.2 | |
| 金星 | 32.7 | 279.5 | 8.3 | -4.1 | |
| 火星 | 56.8 | 259.5 | 2.7 | 1.3 |
※ 惑星は地平線上の5惑星のみ表示。
コラム: 「上弦」の語源
半月講は毎月、上弦の日の夜に実施します。2023年半月講ページのコラムにも書いたとおり、月を観察しやすいのが最大の理由です。ではこの「上弦」は、どこから来た言葉でしょうか。
半月は2回あるのにお気づきでしょうか。
新月に始まり、少しずつ大きくなって半月に、そしてやがて満月に至ります。この新月から満月に至る途中の半月を「上弦」と呼びます。
そして満月は次第にかけていき、半月を経て新月に戻ります。この満月から新月に至る途中の半月が「下弦」です。
上弦は東側が欠けて西側が光っているのに対し、下弦は逆に東側が光って西側が欠けているのが特徴です。
この上弦という言葉がいつ頃から使われているかを調べてみたところ、平安時代中期の9世紀末に編纂された「田氏家集」に出ていることがわかりました(※1)。田氏家集は島田忠臣の詩文をまとめたものですので、この頃にはすでに一般的な用語として使われていたことが伺えます。なお、大和言葉としては「カムツユミハリ」と読むそうです(※2)。
さらに由来を遡ってみようと思ったんですが、これ以上はよくわからず、中国由来なのか日本で生まれた言葉なのかも判別がつきませんでした。ただ、現代中国語には日本語と同じ意味で上弦という単語があります(※3)。
さて本題の語源については諸説あるようですが、半月を、弦を張った弓に見立てているのは共通しています。孤の部分が弓の本体、直線部分が弦というわけですね。
現在では大きく二つの説が有力のようです。
まずひとつめは、月が沈むときの姿について(※4)。月が沈むとき、上弦は直線の側を上にして沈みます。月を弓に見立てると、弦が上の姿で沈むところから上弦と呼ぶようになったという説です。
それに対して下弦は、弦を下にして沈みます。
また、「三日月」や「十五夜」のように月齢に由来するという説もあります(※5)。月は新月を月齢0としてスタートし、月齢7の上弦、月齢15の満月を経て、また新月に戻ります。月齢の前半、つまり上旬の半月を上弦、後半の半月を下弦と呼ぶようになったという説です。
参考文献
※1 日本国語大辞典
※2 古事類苑 天部 洋巻 第1巻
※3 ポケットプログレッシブ中日・日中辞典
※4 仙台市天文台
※5 日立シビックセンター

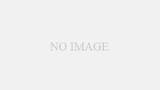

コメント